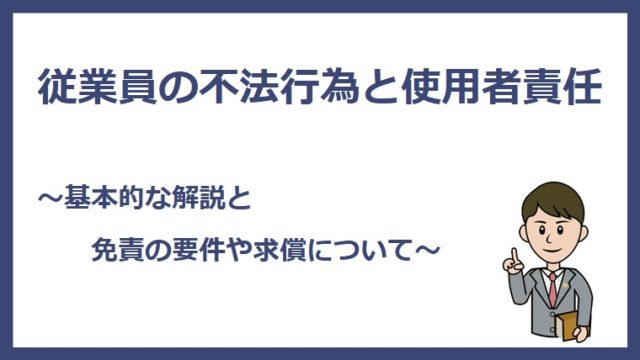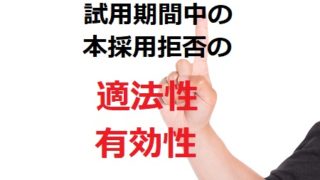従業員数が多くなってくると、ときに従業員が逮捕されるという事態に会社が直面することがあります。
このような非常時こそ冷静な対応が必要です。本記事では、弁護士が従業員が逮捕された際の会社の対応について解説します。
報道資料等の収集、従業員との面会
会社が従業員の逮捕を知るきっかけは次のものがありえます。また、会社や他の従業員が被害者であるなど既に会社が情報を把握している場合もあるでしょう。
- 新聞、テレビ、ネットニュース等の報道、メディアからの取材
- 従業員の家族や知人からの連絡
- 警察・検察などの捜査機関からの連絡
- 顧客、取引先、関係者等からの問い合わせ
- 従業員の弁護人からの連絡
会社にとって突然の逮捕の場合は、従業員と面会して話を聞かないことには分からないことだらけですので、まずは従業員との面会をこころみます。
また、すべて鵜呑みにすることはできませんが、警察発表や報道資料を入手することで情報収集も可能です。ネットニュースや警察のウェブサイトでの発表では氏名等詳細が載っていない場合でも、地元新聞などでは実名報道されていることも多いです。
従業員に会えるのはいつから?
被疑者として身柄拘束を受けている従業員に面会ができるのは、被疑者が勾留という逮捕後の身柄拘束手続きを取られてからです。勾留手続がとられるのは逮捕後72時間以内ですので、逮捕されてから長くて3日後には従業員に面会できるようになります。ただし、弁護人以外との面会が禁じられている場合もあり、その場合は面会はできません。
また、逮捕後勾留されずに釈放されることもあります。この場合は、従業員と連絡が取れる限りは面会に支障はないでしょう。身柄拘束はされていないものの音信不通となってしまった場合は、無断欠勤等による解雇等を検討する必要が出てきます。
身柄拘束場所を確認
逮捕・勾留された場合は、各警察署の留置場か拘置所で被疑者は身柄拘束を受けます。多くの場合は、逮捕した警察署の留置場で身柄拘束がされます。
報道などで逮捕された警察署が分かっている場合は、その警察署の留置管理に連絡をすれば、面会手続について教えてもらえます。面会時間など細かな点が施設によって違うので、必ず事前に連絡をして確認しまししょう。
面会の際の主な注意事項は次のとおりです。
- 面会時間は15~30分程度
- 平日の日中のみ
- 警察署職員等の立ち合い有り
面会の際に確認すべきこと
上記のとおり、被疑者との面会時間は限られていますので、あらかじめ聞くべきことを端的にまとめておくことが重要です。主に聞いておくべき点は次の点です。
- 被疑事実及びその認否
- 弁護人の氏名、事務所
- 今後の見込み
- 退職の意向の有無
被疑事実及びその認否
報道や警察発表では被疑事実の詳細は分からないことも多く、会社がなにがしかの処分を下すにしても本人の弁解を聴取する必要があるので、まずは被疑事実と本人の認否を確認します。
弁護人の氏名、事務所
連絡を取り合うことがありえるので、弁護人の氏名、事務所は確認しておきましょう。
今後の見込み
起訴されて身柄拘束が長期化しそうなのか、不起訴・略式罰金などですみそうなのか等、被疑者は今後の見込みを弁護人から説明されているはずですので、確認しましょう。
退職の意向の有無
会社の解雇事由に該当する場合は、解雇することも考えられますが、従業員が自主的に退職の意向を示すケースも多いです。解雇の有効性なども考慮の上、自主退職処理とすることも検討する必要があるため、従業員の意向を確認しておきましょう。退職届の差し入れも可能です。
身柄拘束期間中、釈放後終局処分までの従業員の扱い
身柄拘束期間中
従業員が身柄拘束を受けている期間中は、従業員は労務を提供できないので、欠勤扱いとしてかまいません。
釈放後終局処分まで
保釈などで身柄拘束を解かれている場合は少々複雑な検討が必要になります。
起訴休職制度がある場合
会社によっては、就業規則に、「刑事事件で起訴された従業員は当該事件が終結するまでの間休職とする。」といった起訴休職制度(休職期間中は無給)が定められていることがあります。
就業規則上の条件をみたす場合は、この制度により休職をさせることも考えられます。
もっとも、裁判例上、起訴休職を無条件で認めているわけではなく、対外的信用及び職場秩序の維持、労務の提供などの理由から業務遂行上の具体的な支障が生ずる場合に限られる等の制限がされている点に注意が必要です(山九(起訴休職)事件、東京地判平成15年5月23日、労判854号30頁)。
逮捕された従業員を解雇することは可能か
逮捕されたからといって、当該従業員が犯罪を犯したとは限りません。本人が認めていない限り、刑事処分が決まるまでに事実関係の調査が不十分なまま会社で処分を決定すると、処分の有効性に問題が生じるおそれがあります。
また、本人が認めていたり、有罪が確定した場合でも解雇が全て適法にできるとは限りません。特に懲戒解雇は厳しく判断されるので、懲戒解雇を行う場合は慎重な検討が必要です。
横領等の会社内での犯罪の場合
横領、他の従業員に対する暴力・性犯罪等、会社内での犯罪がなされた場合、懲戒解雇・普通解雇ともに有効にできることが多いでしょう。
ただし、懲戒解雇をするには就業規則の根拠規定と周知が必要になります。
飲酒運転・痴漢等、DV等私生活上の非行
私生活上の非行であっても、事業活動に直接関連を有するものや会社の社会的評価に影響をもたらすものは懲戒処分の対象になりえます。
業務外での飲酒運転は企業等の処分も厳しい傾向にあり、ドライバーなど業務が運転に関わる職種においては、懲戒解雇も有効とされていますが(東京地判平成19年8月27日、ヤマト運輸事件)、ドライバーなどではない場合は懲戒解雇が無効と判断されることもありますので、注意が必要です(加西市(職員・懲戒免職)事件大阪高判平成21年4月24日、労判983号88頁)。
痴漢に関しては諭旨解雇が無効とされた裁判例があります(東京メトロ(諭旨解雇・本訴)事件、東京地判平成27年12月25日、労判1133号5頁)。
私生活上の非行については、当該従業員の日ごろの勤務態度、前科前歴の有無、当該行為の悪質性やメディア報道による会社の社会的評価の毀損の有無などを考慮して、処分が重すぎないかどうかを判断する必要があります。
メディア対応
会社の事業内容や規模、犯罪の性質によっては報道がされたり、メディアからの取材を受けることがあります。
報道がされるタイミングとしては、逮捕時、起訴時、判決時などがありますが、逮捕時がほとんどで、その後も報道が続くケースは重大なケースで数としてはあまりありません。
もし、メディアからの取材の電話等があった場合は、初期の時点では会社としても事実関係は定かになっておらず、従業員のプライバシーの問題等もありますので、具体的なコメントは差し控えておくべきです。